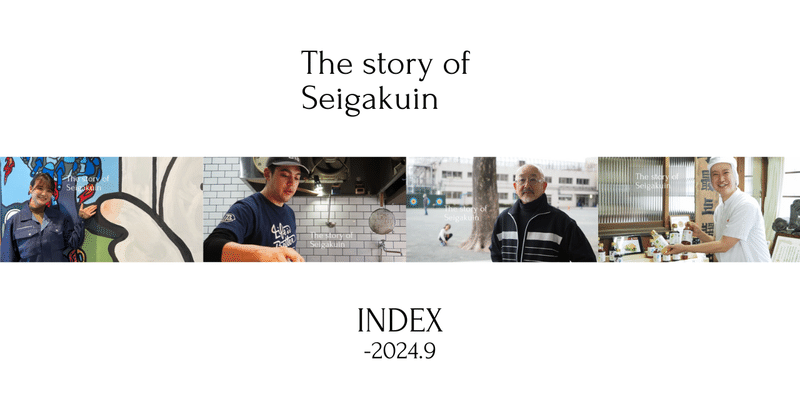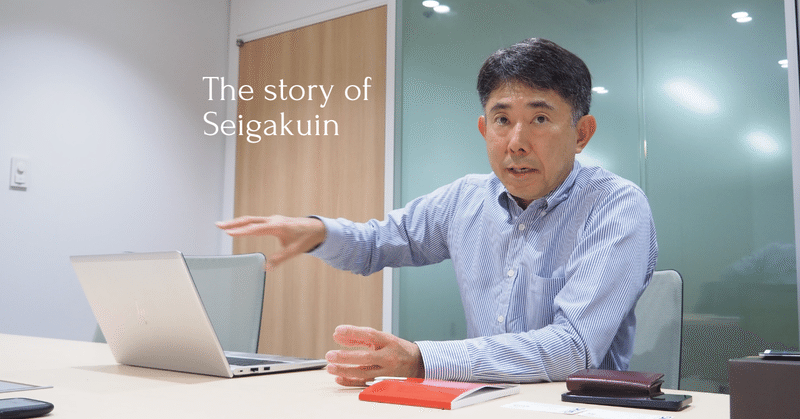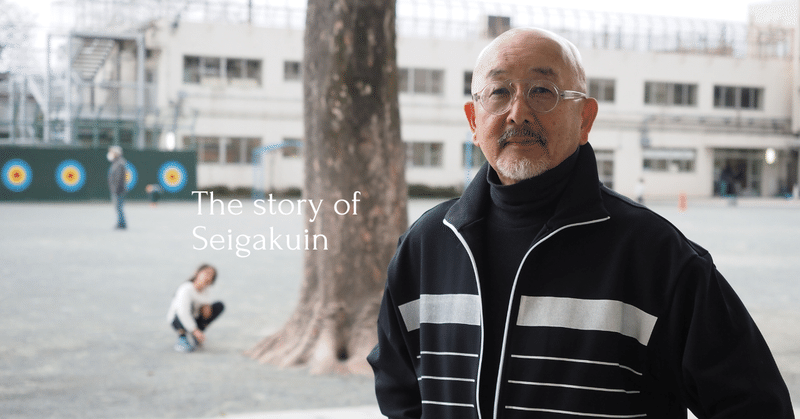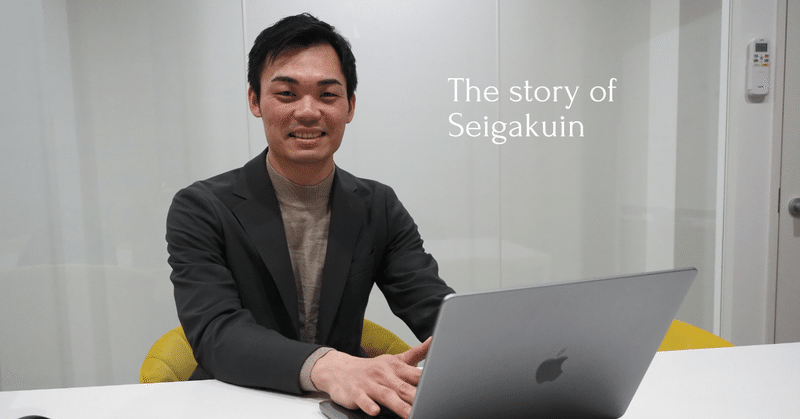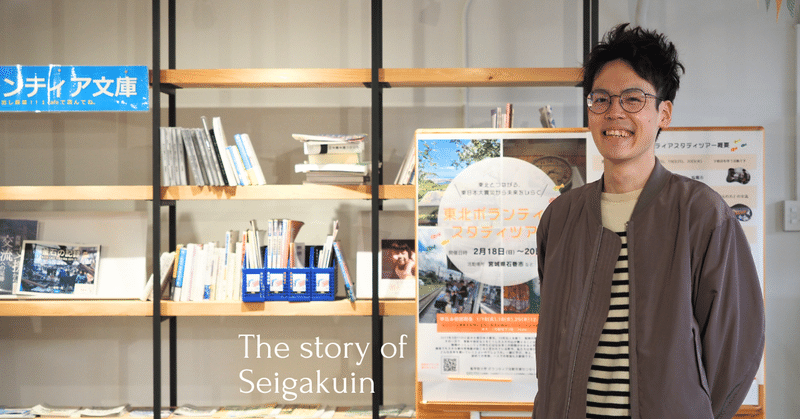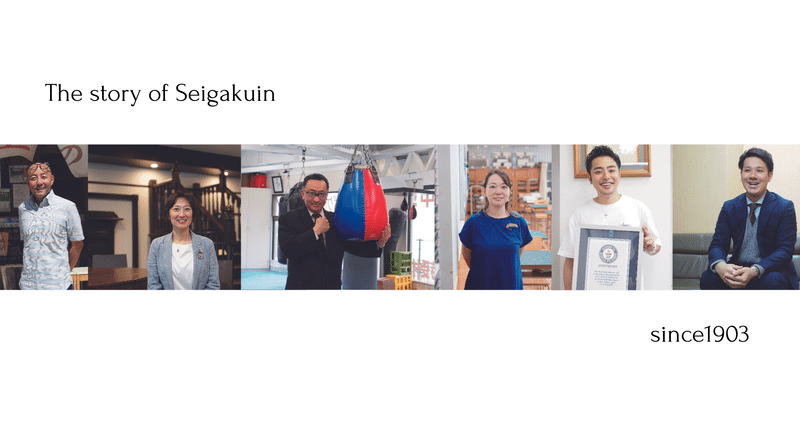
たくさんの聖学院の卒業生が社会で活躍しています。卒業生は聖学院の宝物であり、めざす教育の答えでもあります。順調なときも、そうでないときも、いつでも聖学院は一緒です。卒業生を誇りに…
- 運営しているクリエイター
記事一覧
固定された記事

「The story of Seigakuin」【番外編】 &Talk われら青春の運動部|加藤 柚子 先生×武井 貴 先生
加藤 柚子 先生 女子聖学院中学校・高等学校 卒業 聖学院広報センターは、卒業生、在校生保護者対象の広報誌『ASF NEWS』を年1回、6月〜7月に発行しています。 2024年(No.62)のASF NEWSでは、読者からリクエストの多い「運動部」を特集しました。 巻頭特集「& Talk」で、男女聖学院中高バスケットボール部(以下バスケ部)顧問のトークセッションを掲載いたしました。 女子聖学院中高のバスケ部顧問の加藤 柚子(かとう ゆずこ)先生は、女子聖学院中高の卒業生